-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年11月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
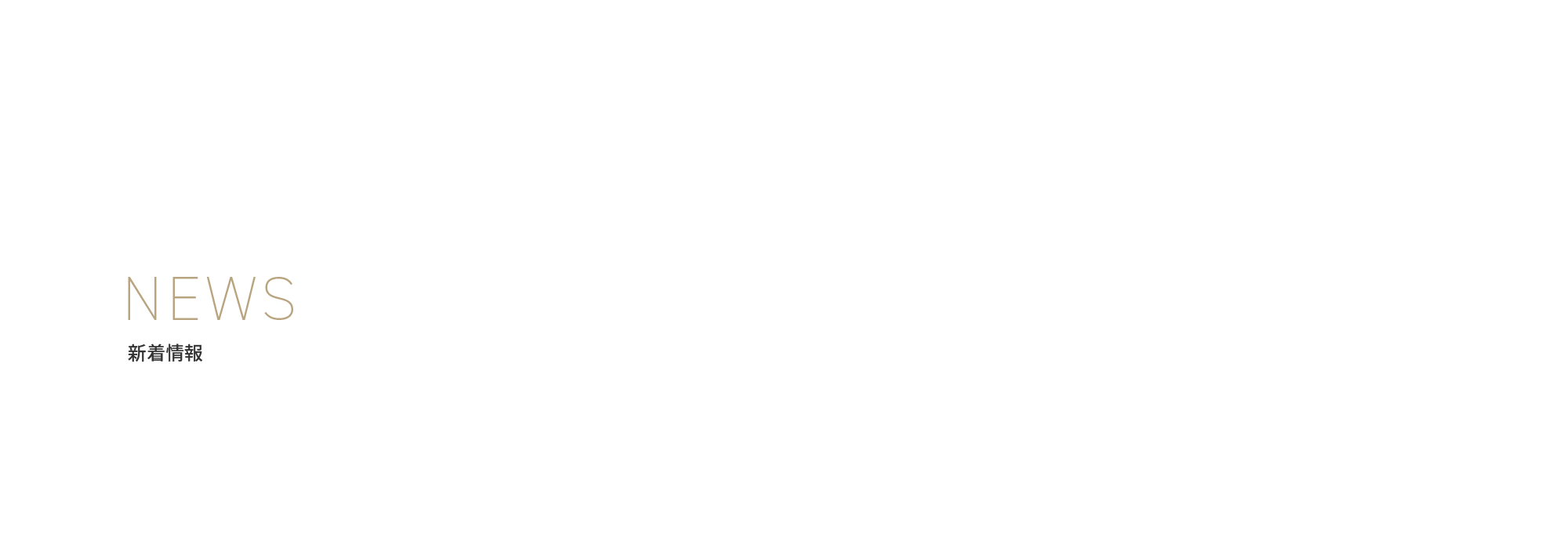
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
目次
自動車整備業の魅力の一つは、お客様の生活に直結する喜びを感じられることです。
車が故障すると、通勤・買い物・送り迎え…日常が一気に不便になります。
そんな中で修理を終え、エンジンが元気よくかかった瞬間、
お客様の表情がパッと明るくなり、「助かったよ」「ありがとう」と声をかけてもらえる──
この瞬間は何度経験しても胸が温かくなります。
車は便利な道具ですが、一歩間違えば大きな事故につながります。
ブレーキパッドやタイヤ、ハンドル操作系統など、安全に直結する部品を点検・整備することは、
運転者だけでなく同乗者、そして道路を行き交うすべての人の命を守ることにもつながります。
この「安全を預かっている」という責任感は、整備士の誇りであり、やりがいの源です。
自動車は年々進化し、整備内容も変化します。
昔はキャブレターやメカニカルな部品が主役だった車も、今や電子制御やハイブリッド・EVが当たり前。
新しい診断機器や特殊工具を使いこなすたびに、自分のスキルが磨かれていることを実感します。
**「一生学び続ける仕事」**という成長感も、自動車整備業ならではの魅力です。
大型修理や事故車修理は、一人では完結しません。
板金・塗装担当、電装担当、メカニック…それぞれが専門性を発揮しながら協力して仕上げます。
予定通りに作業が終わり、お客様に納車できたときのチーム全員の達成感は格別です。
車が好きな人にとって、毎日いろいろな車に触れられる環境は夢のようです。
最新モデルの試運転、珍しいクラシックカーの整備、特殊なチューニング依頼…
趣味と仕事が一体化する瞬間が多く、「好きなことを仕事にできる」喜びを味わえます。
自動車整備業のやりがいは、
お客様の感謝が直接届く
命と安全を守る責任感
技術の進化を学び続けられる
チームで達成感を共有できる
車への情熱を日々満たせる
という、多面的な魅力にあります。
ただの“修理屋”ではなく、人の暮らしと安全を支える技術者として誇れる仕事──
それが自動車整備業です。
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
目次
自動車整備業で行われる修理は、大きく以下の3つに分けられます。
機能修理(メカニカル系)
エンジン、ブレーキ、ミッションなど走行や安全に直結する部分の修理。
外装・板金修理(ボディ系)
衝突や擦れによる外板の凹み・傷の修復、塗装の再施工など。
電装系修理
カーナビ、ライト、パワーウィンドウ、電子制御部品など電気系統の修理。
この分類は修理内容だけでなく、必要な専門知識・工具・工程にも大きく影響します。
例:エンジン不調の修理
症状確認・ヒアリング
「加速が鈍い」「異音がする」など、オーナーからの情報を詳細に収集。
診断
OBD(車載診断機)でエラーコードを読み取り、目視点検や試運転で不具合箇所を特定。
分解・点検
必要な箇所だけを分解し、摩耗・破損状況を確認。
部品交換・修理
純正部品やリビルト部品を用いて交換、もしくは研磨・再調整。
組付け・調整
トルク管理をしながら組み直し、アイドリングや加速性能を確認。
最終チェック・納車
試運転と再診断で問題がないことを確認して納車。
例:バンパーとフェンダーの凹み修理
損傷確認・見積り作成
目視と計測で変形範囲を特定し、部品代・工賃を算出。
分解作業
周辺部品(ヘッドライトやグリル)を外して作業スペースを確保。
板金成形
専用工具で金属や樹脂パネルを元の形に近づける。
パテ成形・研磨
微細な歪みをパテで整え、表面を研磨。
下地塗装(サフェーサー)
防錆と塗料密着性向上のために塗布。
本塗装・乾燥
車体色に合わせて調色し、塗装ブースで吹き付け、乾燥。
組み付け・仕上げ磨き
外した部品を戻し、表面を磨き上げて納車。
症状確認
ロービーム・ハイビームのどちらが点かないかを確認。
原因特定
バルブ切れ、配線断線、リレーやスイッチの不良などをテスターで調べる。
部品交換・配線修理
必要に応じてバルブやユニットを交換、配線を補修。
点灯テスト・調整
光軸を規定値に合わせ、夜間走行に支障がないかを確認。
納車
修理内容と交換部品を説明し、安全運転を促す。
安全第一:ブレーキやタイヤなど安全部品は必ず規定値を満たすまで修理。
品質管理:部品組付け時のトルク、塗装後の色ムラ、電装系の動作確認などを徹底。
お客様への説明:修理前・修理後の状態を写真や部品現物で見せると信頼度が高まる。
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
ということで、自動車整備において最も重要な作業や点検 について、プロの視点から詳しく解説します♪
自動車整備業は、単なる車の修理ではなく、安全な走行を維持し、事故を未然に防ぐための重要な役割を果たす業界 です。
適切な整備や点検を怠ると、ブレーキの故障やエンジンのトラブルなど、命に関わる重大な事故を引き起こすリスク があります。
ブレーキやタイヤの摩耗、ハンドル操作の異常などを事前に発見
適切な点検・整備を行うことで、重大事故のリスクを低減
運転者だけでなく、歩行者や同乗者の命を守るためにも不可欠
オイル交換や定期的なメンテナンスでエンジンや駆動系の負担を軽減
異常を早期発見することで、高額な修理費を回避
中古車の価値を維持し、売却時の査定額アップにもつながる
タイヤの空気圧調整やエンジンの調整で燃費を向上
排ガス規制に対応し、環境への負荷を低減
EV・ハイブリッド車のバッテリー管理も重要な整備項目
ブレーキパッド・ディスクローターの摩耗チェック
レーキフルード(油圧ブレーキの作動液)の交換
ブレーキキャリパーの動作確認(固着や異常がないか)
なぜ重要か?
ブレーキの異常は、制動距離の増加やブレーキの利きが悪くなる原因となり、重大事故を招く可能性があります。特にブレーキパッドは5mm以下になると交換推奨 です。
空気圧チェック(適正な空気圧を維持することで燃費向上)
溝の深さチェック(スリップサインが出たら交換)
偏摩耗やひび割れの確認
なぜ重要か?
タイヤの状態が悪いと、スリップ事故やパンクの原因になります。残り溝が1.6mm未満になると車検不適合 となるため、定期的な確認が必要です。
適切なオイル交換サイクル(通常5,000~10,000kmごと)
フィルター交換でエンジン内部の汚れを防ぐ
オイルの粘度や劣化状態の確認
なぜ重要か?
エンジンオイルはエンジンの潤滑・冷却・清掃を行う役割を担っています。劣化するとエンジン内部の摩耗が進み、燃費の悪化や最悪の場合エンジン故障の原因 になります。
電圧チェック(12.5V以下は要注意)
端子の腐食チェック(サビがある場合は清掃)
バッテリー液の量確認
なぜ重要か?
バッテリーが弱ると、エンジン始動が困難になり、突然の故障につながります。特に冬場はバッテリーの性能が低下しやすいため、点検が不可欠 です。
冷却水(クーラント)の量と濃度の確認
ラジエーターやホースの漏れチェック
サーモスタットの作動確認
なぜ重要か?
冷却系統が正常に作動しないと、エンジンが過熱し、最悪の場合オーバーヒートで故障 してしまいます。冷却水は2~3年ごとに交換が推奨 されます。
ファンベルト・タイミングベルトの摩耗や亀裂の確認
適正な張り具合(緩みすぎや張りすぎは故障の原因)
異音(キュルキュル音)が発生していないか
なぜ重要か?
エンジンの補機類(オルタネーター、ウォーターポンプ、パワーステアリング)を駆動するベルトは、切れると車が動かなくなる重大な故障を引き起こします。特にタイミングベルトは、10万kmごとの交換が推奨 されています。
ヘッドライト・テールランプ・ウィンカーの点灯確認
ワイパーゴムの劣化チェック(ゴムが切れている場合は交換)
ウォッシャー液の補充
なぜ重要か?
夜間の視界確保や、他の車両・歩行者への意思表示にはライトが欠かせません。また、ワイパーが劣化すると雨の日の視界が悪化し、事故のリスクが大幅に上がる ため、半年~1年ごとの交換が推奨 されます。
最も重要な点検項目は「ブレーキ・タイヤ・オイル・バッテリー」
冷却系統やベルト類の点検も欠かせない
ライトやワイパーは安全運転の基本、定期的に確認すべき
定期メンテナンスを行うことで、車の寿命を延ばし、修理費用を抑えられる
プロの整備士による定期点検と適切なメンテナンスが、あなたのカーライフを支える鍵 です。安全で快適なドライブのために、定期点検を怠らないようにしましょう!
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
今回は、未来の自動車整備についてです。
車の世界もどんどん進化していますよね。
最近では電気自動車(EV)やハイブリッド車が増えてきて、「これからの自動車整備はどうなるんだろう?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
今回は、未来の自動車整備について、最新のトピックをフレンドリーにお届けします!
車の整備がどんなふうに進化していくのか、一緒に想像してみましょう!
電気自動車(EV)の整備
最近、街中でEV(電気自動車)を見かけることが増えてきましたよね。
環境に優しいだけでなく、静かで快適な乗り心地が魅力のEVですが、実は整備の内容がこれまでのガソリン車とは大きく異なるんです。
1. EV整備の中心はバッテリーとモーター
ガソリン車の整備といえば、エンジンやオイル交換が主な作業でした。
しかし、EVにはエンジンがなく、代わりに「バッテリー」と「モーター」が車の心臓部を担っています。
このため、整備のポイントも大きく変わります。
バッテリーの点検とメンテナンス
EVのバッテリーは車を動かすためのエネルギー源。
バッテリーの劣化状態や充電効率を定期的にチェックする必要があります。
また、気温の変化や使用頻度によってバッテリーの性能が変わるため、プロの点検が欠かせません。
モーターの整備
モーターはエンジンの代わりに車を動かす重要な部分です。
駆動系の部品や冷却システムのメンテナンスも含め、細かなチェックが求められます。
2. 冷却システムの重要性
EVはモーターやバッテリーが熱を持ちやすいので、冷却システムが非常に重要です。
ラジエーター液のチェックや冷却システム全体のメンテナンスを怠ると、バッテリーの寿命が短くなったり、車全体の性能が落ちることも。
3. ソフトウェアのアップデートも整備の一環に
EVはコンピューター制御が非常に重要な役割を果たしているため、整備内容に「ソフトウェアのアップデート」が加わりました。
スマートフォンのアプリを更新するように、車のシステムを最新の状態に保つことで、より安全で快適に走行できます。
未来のドライバーへのメッセージ
「EVって整備が難しそう…」と不安になるかもしれませんが、整備工場やディーラーでは専用の設備や知識を持ったスタッフが対応してくれるので安心してください。
これからは「ガソリンスタンドに行く」感覚で、気軽にEVの点検をお願いする時代になりそうですね!
AIとデジタル化で効率アップ
未来の整備では、AIやデジタル技術が大活躍する時代がやってきます。
これまで整備士さんが時間をかけて調べていたことを、AIがスピーディーに解決してくれるようになるんです。
1. AI診断システムの登場
最近では、車に搭載されたセンサーやカメラがリアルタイムで車の状態を監視し、不具合があればAIが自動で診断するシステムが開発されています。
どんなことが分かるの?
例えば、エンジンやバッテリーの異常、タイヤの空気圧低下、ライトの故障などをAIが瞬時に検出。
「あと何キロ走れるのか」や「どの部品を交換すべきか」まで詳しく教えてくれるんです!
メリット
これまで車のトラブルを特定するのに時間がかかっていた整備が、より短時間で正確に行えるようになります。
ドライバーにとっても、トラブルを未然に防ぐ大きな安心材料になりますね!
2. AR(拡張現実)を活用した整備
整備士さんがARゴーグルをかけると、目の前に車の内部構造が3Dで映し出され、どの部品が異常かを一目で確認できる技術も進化しています。
まるでSF映画のような世界ですが、これが現実になりつつあるんです!
具体的な活用例
整備士さんがARゴーグルを装着すると、配線やパーツの情報が目の前に表示され、修理手順や注意点がリアルタイムで案内されます。
初心者の整備士でも高度な修理ができるようになるのはすごいことですよね!
3. 自動化された整備ロボットの活躍
一部では、タイヤ交換やオイル交換をロボットが自動で行う試みも始まっています。
人が手作業で行うよりもスピーディーかつ正確に作業が進むため、待ち時間が短縮されるのは嬉しいポイントです。
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社、更新担当の岡です。
日が長くなってきたとはいえ、雨や夕暮れの時間帯の運転では「ライト」が頼りになりますよね。
でも、「点いていると思っていたのに、実は切れていた」「なんだか暗くて見えにくい」…そんな経験はありませんか?
今回は、ヘッドライト・ブレーキランプ・ウインカーなど灯火類の点検とメンテナンスについてご紹介します!
目次
ライト類は、あなたが「見える」ようにするだけでなく、他のドライバーや歩行者からも「見られる」ことで交通の安全を守っています。
主な灯火類と役割:
ヘッドライト:夜間の前方視界を確保
スモールランプ(車幅灯):薄暗い時間帯の存在アピール
ブレーキランプ:減速・停止を後方に伝える
ウインカー(方向指示器):進路変更・曲がる合図
バックランプ:後退中の警告と周囲照らし
どれかひとつでも不点灯になると、重大な事故や違反につながる可能性があります。
以下のような症状は見逃し注意です:
ライトが突然つかなくなった
ヘッドライトの明るさが左右で違う
テールランプが暗くなっている
ウインカーの点滅が早い or 遅い
ヘッドライトが黄ばんでくすんでいる
原因の多くは、
バルブ(電球)の寿命
配線の断線や接触不良
ソケットの腐食やサビ
レンズの劣化・汚れ
特にヘッドライトの黄ばみやくすみは、古い車によく見られる現象で、光量不足や車検不合格の原因にもなります。
自分でも簡単にできるチェック方法をいくつかご紹介します:
エンジンをかけた状態で、車の前後を一周しながらライトが全て点いているか確認
ウインカーやブレーキランプは、壁の反射や家族・友人に見てもらうのも◎
夜間、暗い場所でヘッドライトの照射範囲や明るさを確認
黄ばみがあればライトクリーナーなどで軽く磨いてみましょう
ちょっとした確認で大きな事故が防げます!
当店では、以下のサービスも承っています:
灯火類のバルブ交換(ハロゲン、HID、LED対応)
ヘッドライトの黄ばみ除去・コーティング
レンズユニットの交換手配
配線不良やソケット接触不良の修理
「どこが悪いのかわからないけど、ちょっと暗い気がする」
「ライトの色味を変えたい」など、ドレスアップのご相談もOKです!
実は、灯火類の不点灯は整備不良車として違反切符の対象になります。
ブレーキランプ1灯不点灯:整備不良
ウインカー点灯しない:進路変更違反になることも
夜間無灯火走行:反則金+点数
整備不良がもとで事故を起こすと、過失割合にも影響します。
やっぱり「点いていて当然」ではなく「点いているか確認」が大切です。
安全運転のためには、「見えること」「見せること」の両方が不可欠です。
日々の運転で“なんとなく不安”を感じたら、それは点検のサインかもしれません。
創栄自動車では、灯火類を含む日常点検や定期整備も承っております。
明るく、安全に走るために、ぜひお気軽にご来店ください!
以上、【見えていますか?見られていますか?灯火類の点検で安心・安全ドライブを!】でした。
次回もお楽しみに!
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社、更新担当の岡です。
ある日突然、メーターに「見慣れないランプ」が点灯してドキッとしたことはありませんか?
中でも特に不安になるのが、エンジンの警告灯(チェックランプ)です。
「すぐに止めるべき? 走っても大丈夫?」
「修理代、高くなるんじゃ…」
そんな不安を抱える方のために、今回はエンジン警告灯が点いたときに確認すべきポイントと、対応の仕方について詳しくご紹介します!
目次
エンジン警告灯は、車の異常を知らせる“初期サイン”です。
車のコンピューター(ECU)がセンサー情報を監視し、異常を感知すると点灯します。
代表的な原因:
O2センサーやエアフロセンサーの故障
点火系や燃料噴射系の異常
排気系(マフラー・触媒)のトラブル
エンジンの制御系トラブル(アイドリング不安定など)
このランプがついたからといって、すぐに壊れるわけではありませんが、放置は禁物です!
結論から言うと、「点滅していなければ走行可能な場合が多い」です。
点灯しているだけ:エンジン制御系の一時的な異常が多く、ゆっくり安全に走行して、速やかに点検を受けましょう
点滅している:重大な異常を知らせている可能性が高く、走行をすぐに中止することが望ましいです
いずれの場合も、できるだけ早く専門の整備工場で診断を受けましょう!
「調子が悪くないから大丈夫でしょ」と油断するのは危険です!
警告灯が出ている間に走り続けると、エンジンや触媒の損傷につながることも
放置したことで修理代が高額になるケースも
車検時に警告灯が点いていると「不合格」になることもあります
ちょっとしたセンサーの不調でも、早めの点検で大きな出費を防げます!
当店では、以下のような専用診断機による点検を実施しています:
警告灯点灯の原因診断(OBD診断)
故障コードの読み取り・消去
センサー類の状態確認
必要に応じた修理や部品交換のご提案
「とりあえず診てもらいたい」という軽い気持ちでのご来店も大歓迎です!
エンジン警告灯を防ぐためには、日頃の点検がやはり基本です。
定期的なオイル交換(劣化したオイルはセンサーを誤作動させることも)
エアクリーナーやスパークプラグの定期交換
長距離運転時の高回転走行での煤(すす)除去
年1回の点検や車検をきっかけに、簡易診断を受けるのもおすすめです
エンジン警告灯が点いたとき、「様子見でしばらく乗る」は一番避けたい対応です。
早めの点検で、
◎修理費を抑える
◎トラブルの芽を摘む
◎安心して車に乗り続けられる
そんなメリットがたくさんあります!
「見慣れないランプが点いた」「ちょっと心配だな」と思ったら、ぜひ創栄自動車にご相談ください!
いつでも皆さまのカーライフを全力でサポートいたします!
以上、【エンジン警告灯が点灯!? 焦らず確認すべきポイントとは】でした。
次回も実用的で役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社、更新担当の岡です。
だんだんと暑さが増してきて、遠出やお出かけが増える時期になりましたね!
そんなときに見落としがちなのが「タイヤの状態」です。
「まだ溝があるから大丈夫」
「パンクしてないし問題ないでしょ」
…そんな風に思っていませんか?
実は、タイヤの劣化や空気圧の異常は、事故や燃費の悪化を引き起こす要因のひとつ。
今回は、安全なドライブに欠かせない、タイヤ点検の重要性についてお伝えします!
目次
タイヤの寿命は「溝の深さ」だけでは判断できません。
一般的な目安は以下の通りです:
使用年数:4〜5年が限界(走行距離に関係なく)
溝の深さ:1.6mm以下で「整備不良」として違反対象
サイド部分にひび割れがあると要注意
タイヤはゴム製品なので、時間が経つと自然に劣化していきます。
特に日差しが強い夏場は、傷みが早く進むこともあります。
タイヤの空気圧も見逃せないポイントです!
空気が少ないと → 燃費が悪化、ハンドルが重くなる
空気が多すぎると → 路面のグリップ力が低下し危険
空気圧が適正でも → 1ヶ月に約5%ずつ自然に減少
つまり、月に1回は空気圧チェックをおすすめしています。
創栄自動車では、無料で空気圧チェックを行っておりますので、お気軽にお立ち寄りください!
タイヤには「スリップサイン」という、安全性の目安となるサインが設けられています。
溝の中に横線のような出っ張りが見えたら、それがスリップサイン
このサインが露出していると、法律上も使用NG!
スリップサインが出る前に、早めの交換を検討しましょう。
夏は路面温度が60℃を超えることもあり、タイヤへの負担が非常に大きくなります。
古いタイヤはゴムが硬くなり、バーストしやすくなる
高速走行時に熱がこもって破裂のリスクが上昇
長距離移動前には必ず点検を!
レジャー前や帰省シーズンの前に、タイヤチェックをぜひお忘れなく!
当店では、
残り溝チェック
空気圧測定
タイヤのひび割れや損傷確認
タイヤ交換やローテーション
など、タイヤに関するすべてのチェック&サービスを行っています!
「まだ使えると思ってたけど、実は危なかった…」なんてことになる前に、ぜひ一度ご相談ください。
タイヤは「唯一、地面と接しているパーツ」。
だからこそ、安全運転のためには定期的な点検が欠かせません。
車のプロがしっかり確認し、お客様に最適なご提案をさせていただきます!
以上、【そのタイヤ、大丈夫?見落としがちなタイヤ点検の重要性】でした。
次回も、お車と安全に長く付き合うための情報をお届けします。お楽しみに!
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社、更新担当の岡です。
暑さが本格化する前に、ぜひチェックしておきたいのが「カーエアコン」です。
「冷房の効きが悪い気がする」
「変なニオイがする…」
そんな症状、放っておくと真夏に後悔することになるかもしれません!
今回は、カーエアコンにまつわるよくあるトラブルと、その予防方法についてご紹介します。
暑さに負けず快適なドライブをするためにも、早めの点検をおすすめします!
目次
エアコンをつけたのに冷たい風が出ない。
そんなときに考えられる主な原因はこちらです:
エアコンガス(冷媒)の不足
コンプレッサー(圧縮機)の故障
ファンやエバポレーターの異常
内部の配管に詰まりや漏れがある
特にエアコンガスは、目に見えないため気づきにくいですが、年数が経つと少しずつ減っていきます。
車内でエアコンを入れた瞬間に嫌なニオイが…という経験はありませんか?
この原因は主に2つ:
エアコン内部にカビが発生している
エアコンフィルターが汚れている
湿気が多い梅雨〜夏場はカビが繁殖しやすい季節です。
対策としては、
定期的なエアコンフィルター交換
エバポレーター洗浄(専用の薬剤による清掃)
を行うことで、快適で衛生的な車内環境を保てます!
エアコンのトラブルは、「冷えない」だけではなく、燃費の悪化にもつながります。
ガス漏れやフィルター詰まりでコンプレッサーが過剰に稼働
結果としてエンジンに負荷がかかる
燃料消費が増える&部品の摩耗も進行
定期的なメンテナンスで、冷却効率アップ+燃費改善も期待できます。
真夏に「冷えない!」と気づいても、修理や部品交換には混雑や納期遅れがつきものです。
創栄自動車では、エアコン点検・ガス補充・フィルター交換・エバポレーター洗浄など、すべて対応可能!
ちょっとでも「効きが悪いかも…」と感じたら、早めにご相談ください!
カーエアコンは、乗っているすべての人の快適さと安全性を支える大事な装備。
とくに小さなお子さまやご高齢の方を乗せる機会がある方は、快適な室温を保つことがとても重要です。
「今年の夏は安心して過ごしたい!」という方は、
ぜひこの時期に、創栄自動車でカーエアコンの健康診断を!
以上、【エアコンの効きが悪い?夏本番前のカーエアコン点検ポイント!】でした。
次回も、愛車と長く快適に付き合うための情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに!
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社、更新担当の岡です。
前回はバッテリートラブルについてご紹介しましたが、今回は「エンジンオイル」に注目してみましょう!
「オイル交換って、本当に必要なの?」
「交換時期の目安がよくわからない…」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
実は、エンジンオイルの管理ひとつで、愛車の寿命や走行性能が大きく変わってくるんです!
今回は、エンジンオイルの基本から交換の目安、放置するとどうなるかまで詳しく解説していきます!
エンジンオイルには、大きく分けて次の4つの役割があります:
潤滑:金属同士の摩擦を減らし、エンジンの摩耗を防止
冷却:走行中に発生する熱をオイルが吸収し、エンジンを冷やす
清浄:エンジン内部にたまる汚れを取り込んで保持
防錆:金属部分のサビを防ぐ
このように、エンジンオイルはまさに“エンジンの血液”のような存在です!
「少しぐらい大丈夫でしょ」と思っていると、意外と大きなトラブルにつながることも。
放置による主なリスク:
燃費が悪くなる
エンジン音がうるさくなる
エンジン内部が汚れ、寿命が縮まる
最悪の場合、エンジンが焼き付いて修理費が高額に…
特に最近の車は静かで快適なため、オイルの異変に気づきにくいこともあります。
車種やエンジンのタイプによって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです:
走行距離:5,000〜7,000kmごと
期間:半年に1回程度
「そんなに走らないんだけど…」という方も、期間での交換をおすすめします。
オイルは走らなくても劣化していくんです。
さらに、オイルフィルターの交換も忘れずに!
フィルターが詰まっていると、新しいオイルの性能が十分に発揮されません。
創栄自動車では、車種に合わせた最適なオイルを選定し、スピーディーかつ丁寧に交換いたします!
「オイルが汚れていないか見てほしい」
「異音がするような気がする」
そんな時も、ぜひお気軽にお立ち寄りください!
定期点検とオイル交換で、あなたの愛車はもっと快適に、もっと長持ちします!
日々のメンテナンスが、愛車の健康寿命を大きく左右します。
エンジンオイルは車の「命を支える存在」。
交換を先延ばしにせず、定期的な点検を心がけましょう!
何か気になることがあれば、いつでも創栄自動車にご相談くださいね!
以上、【エンジンオイルの役割と交換時期の目安】でした!
次回もお楽しみに!
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社、更新担当の岡です。
本日は【自動車整備雑学講座】をお届けします!
今回のテーマは、
「バッテリーの寿命とトラブル予防法」です。
「ある日突然、エンジンがかからない!」
そんなバッテリートラブル、経験したことありませんか?
特に気温の変化が激しい時期や、車の使用頻度が少ない方は注意が必要です。
今回は、バッテリーの寿命の見極め方と、突然のトラブルを防ぐためのポイントを詳しくご紹介します!
一般的に、自動車用バッテリーの寿命は2〜5年程度。
使用状況や車種、走行距離によっても異なりますが、3年を過ぎたら注意が必要です。
劣化のサイン:
エンジンの始動が遅い・重い
パワーウィンドウやライトの動きが鈍くなる
車内灯の明るさが不安定
バッテリー本体に膨らみや液漏れがある
このような症状が出ていたら、バッテリー交換のタイミングかもしれません!
バッテリー上がりの主な原因は以下の通りです。
ライトの消し忘れ(特にルームランプ)
長期間の未使用
走行距離が極端に短い(発電が追いつかない)
冬場の気温低下による性能低下
ナビやドラレコなど電子機器の電力消費
「走っているのにすぐバッテリーが上がる…」という場合は、オルタネーター(発電機)の不具合も考えられます。
バッテリーは「乗っていれば自然に充電される」と思いがちですが、それだけでは足りないことも。
メンテナンスポイント:
定期的に車に乗る(最低でも週1回、20分以上)
点検時に電圧や比重を測ってもらう
端子部分のサビ・白い粉(硫酸鉛)をチェック
電装品を使いすぎない(エンジン停止中のエアコンやオーディオなど)
創栄自動車では、無料のバッテリーチェックも実施中です!
最近では、アイドリングストップ車専用バッテリーや、より高性能な「長寿命バッテリー」も登場しています。
「長く乗りたい」「頻繁にエンジンかけたくない」という方には、性能の良いバッテリーへの交換を検討してみてはいかがでしょうか?
バッテリーのトラブルは、ある日突然やってきます。
だからこそ、「早めの点検・早めの交換」が一番の安心材料です。
「最近ちょっとエンジンがかかりにくいかも…」と感じたら、お気軽に創栄自動車までご相談ください!
専用の診断機で、バッテリーの状態をすぐにチェックいたします!
以上、【バッテリーの寿命とトラブル予防法】でした!
次回もどうぞお楽しみに!