-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
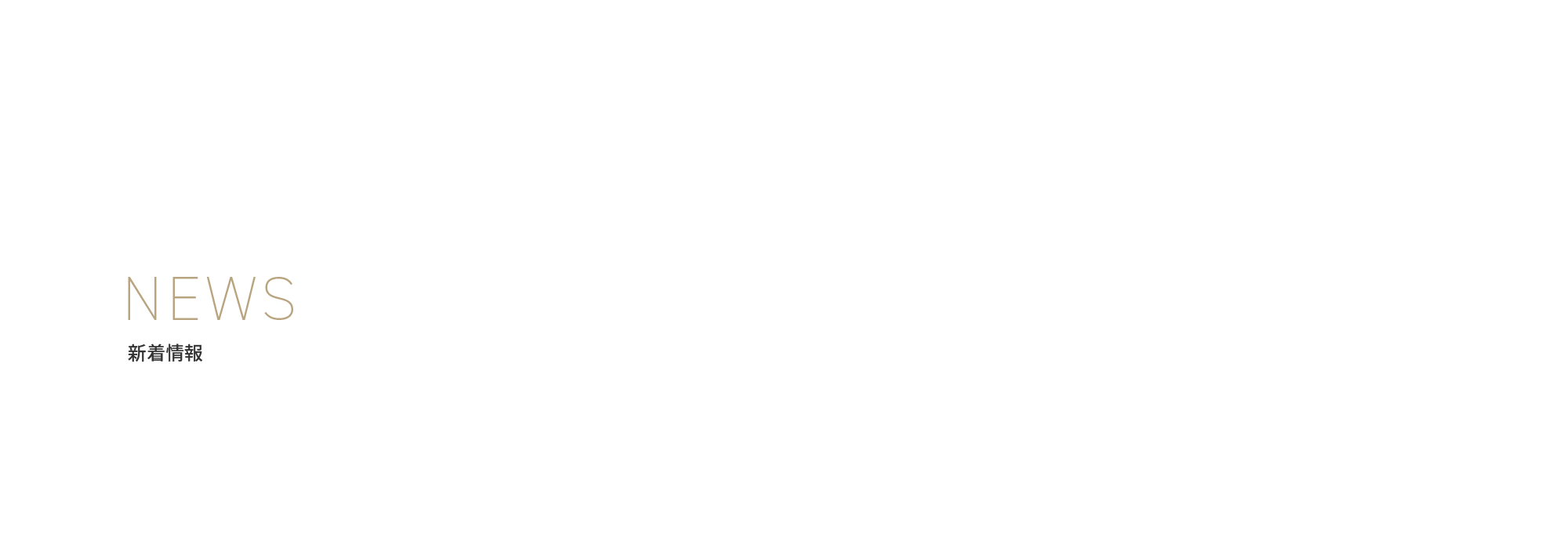
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
自動車整備は、車という命を運ぶ機械を扱う仕事です。
一つのミスが重大な事故や損害に直結する可能性があります。
そのため、作業の正確性はもちろん、安全管理・品質管理・お客様対応・法令遵守すべてにおいて高い意識が求められます。
ジャッキアップ時のウマ(リジッドラック)設置は必須
高温部品や回転部品への不用意な接触防止
電装作業時はバッテリー端子を外し、ショートや感電を防ぐ
トルクレンチで規定値を守る
外したボルト・ナットの混同防止(作業エリアごとに仕分け)
新旧部品の確認と記録
修理後は必ず試運転を行い、異音・異常挙動・警告灯の有無を確認
ブレーキやステアリング系統は特に慎重にチェック
メーカーの整備書やサービスマニュアルを参照し、独断の省略や自己流作業は避ける。
特に新型車は電子制御部品が多く、専用の診断機や手順が必須。
純正部品または信頼できる社外部品を使用
互換品を使う場合は適合情報を必ず確認
同じ箇所の不具合が繰り返される場合、部品だけでなく周辺機構や使用環境も調査。
自動車整備士資格に応じた作業範囲を守る(無資格作業の禁止)
車検や整備記録簿の正しい記載
廃油・廃タイヤ・バッテリーなどの産業廃棄物は法令に沿って処理
排気ガス規制やリコール制度への対応
修理内容・費用・納期を事前に明確に説明
作業後に整備箇所を写真や部品で見せ、透明性を確保
追加修理が必要な場合は必ず了承を得てから実施
納車後もアフターフォローの連絡を行うと信頼度が向上
作業引き継ぎ時の口頭伝達だけでなく、整備記録や指示書への明記
作業場の整理整頓(工具・部品の置き忘れは事故や作業ミスの原因)
新人や異動スタッフへの安全指導の徹底
作業者の安全
車両の品質と安全性
お客様からの信頼
法令・環境保全
すべてを守るための基盤です。
ミスを防ぐための意識と仕組みを日々磨き、
「安全第一・品質確保・誠実対応」の三本柱を徹底することが、長く信頼される整備工場の条件です。
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
自動車整備業は、車の安全・性能を維持するだけでなく、環境保護にも直結する業種です。
整備の現場では廃油や廃タイヤ、使用済みバッテリーなど、多くの廃棄物が発生します。
それらを適切に処理しなければ、大気や土壌、水質の汚染につながるため、整備業者には厳しい環境管理が求められています。
整備工場で発生する主な廃棄物と環境配慮の方法は以下の通りです。
廃油
エンジンオイルやギアオイルは、産業廃棄物として回収・再生燃料や再生油にリサイクル。
廃タイヤ
再生ゴム製品や燃料として再利用。焼却時の有害ガス排出を防ぐため、適切な施設へ搬出。
使用済みバッテリー
鉛やプラスチックを分別・再資源化。鉛は新しいバッテリーの原料として循環。
廃フィルター・部品
金属部分はスクラップとして再利用、フィルター部は適正処理。
これらは法律に基づき管理簿やマニフェストで記録し、**“排出から最終処理までのトレーサビリティ”**を確保します。
自動車整備は、ただ壊れた部品を交換するだけではありません。
適切な整備は燃費改善や排ガス削減につながり、環境負荷を下げる効果があります。
エンジンや燃料系統の清掃で燃焼効率UP → CO₂排出量削減
タイヤの適正空気圧管理で燃費向上&摩耗減少
排気系装置(触媒・DPFなど)の点検で有害ガス排出を抑制
こうした整備は環境だけでなく、お客様のランニングコスト削減にも直結します。
最近では、解体車両から回収した部品を点検・整備して再利用する**リサイクル部品(リユース部品)**の活用が進んでいます。
これにより、
部品製造時のエネルギー消費削減
廃棄物の減量化
修理費用の低減
という三つのメリットが得られます。
整備工場自体の環境負荷を減らす取り組みも増えています。
LED照明や省エネ設備の導入
水性塗料の使用でVOC(揮発性有機化合物)排出削減
雨水利用や節水システムによる洗車用水の節約
こうした努力は、小さな積み重ねですが、長期的に見ると大きな環境保全効果を生みます。
自動車整備業は、車の安全と性能を守ると同時に、廃棄物管理・省エネ整備・リサイクル推進を通じて環境保全にも貢献しています。
今後はEVやハイブリッド車の普及に伴い、新しい廃棄物やリサイクル課題も出てきますが、
その一つひとつに取り組むことが、整備業の社会的価値をさらに高めていくでしょう。
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
自動車整備業の魅力の一つは、お客様の生活に直結する喜びを感じられることです。
車が故障すると、通勤・買い物・送り迎え…日常が一気に不便になります。
そんな中で修理を終え、エンジンが元気よくかかった瞬間、
お客様の表情がパッと明るくなり、「助かったよ」「ありがとう」と声をかけてもらえる──
この瞬間は何度経験しても胸が温かくなります。
車は便利な道具ですが、一歩間違えば大きな事故につながります。
ブレーキパッドやタイヤ、ハンドル操作系統など、安全に直結する部品を点検・整備することは、
運転者だけでなく同乗者、そして道路を行き交うすべての人の命を守ることにもつながります。
この「安全を預かっている」という責任感は、整備士の誇りであり、やりがいの源です。
自動車は年々進化し、整備内容も変化します。
昔はキャブレターやメカニカルな部品が主役だった車も、今や電子制御やハイブリッド・EVが当たり前。
新しい診断機器や特殊工具を使いこなすたびに、自分のスキルが磨かれていることを実感します。
**「一生学び続ける仕事」**という成長感も、自動車整備業ならではの魅力です。
大型修理や事故車修理は、一人では完結しません。
板金・塗装担当、電装担当、メカニック…それぞれが専門性を発揮しながら協力して仕上げます。
予定通りに作業が終わり、お客様に納車できたときのチーム全員の達成感は格別です。
車が好きな人にとって、毎日いろいろな車に触れられる環境は夢のようです。
最新モデルの試運転、珍しいクラシックカーの整備、特殊なチューニング依頼…
趣味と仕事が一体化する瞬間が多く、「好きなことを仕事にできる」喜びを味わえます。
自動車整備業のやりがいは、
お客様の感謝が直接届く
命と安全を守る責任感
技術の進化を学び続けられる
チームで達成感を共有できる
車への情熱を日々満たせる
という、多面的な魅力にあります。
ただの“修理屋”ではなく、人の暮らしと安全を支える技術者として誇れる仕事──
それが自動車整備業です。
皆さんこんにちは!
創栄自動車株式会社です。
自動車整備業で行われる修理は、大きく以下の3つに分けられます。
機能修理(メカニカル系)
エンジン、ブレーキ、ミッションなど走行や安全に直結する部分の修理。
外装・板金修理(ボディ系)
衝突や擦れによる外板の凹み・傷の修復、塗装の再施工など。
電装系修理
カーナビ、ライト、パワーウィンドウ、電子制御部品など電気系統の修理。
この分類は修理内容だけでなく、必要な専門知識・工具・工程にも大きく影響します。
例:エンジン不調の修理
症状確認・ヒアリング
「加速が鈍い」「異音がする」など、オーナーからの情報を詳細に収集。
診断
OBD(車載診断機)でエラーコードを読み取り、目視点検や試運転で不具合箇所を特定。
分解・点検
必要な箇所だけを分解し、摩耗・破損状況を確認。
部品交換・修理
純正部品やリビルト部品を用いて交換、もしくは研磨・再調整。
組付け・調整
トルク管理をしながら組み直し、アイドリングや加速性能を確認。
最終チェック・納車
試運転と再診断で問題がないことを確認して納車。
例:バンパーとフェンダーの凹み修理
損傷確認・見積り作成
目視と計測で変形範囲を特定し、部品代・工賃を算出。
分解作業
周辺部品(ヘッドライトやグリル)を外して作業スペースを確保。
板金成形
専用工具で金属や樹脂パネルを元の形に近づける。
パテ成形・研磨
微細な歪みをパテで整え、表面を研磨。
下地塗装(サフェーサー)
防錆と塗料密着性向上のために塗布。
本塗装・乾燥
車体色に合わせて調色し、塗装ブースで吹き付け、乾燥。
組み付け・仕上げ磨き
外した部品を戻し、表面を磨き上げて納車。
症状確認
ロービーム・ハイビームのどちらが点かないかを確認。
原因特定
バルブ切れ、配線断線、リレーやスイッチの不良などをテスターで調べる。
部品交換・配線修理
必要に応じてバルブやユニットを交換、配線を補修。
点灯テスト・調整
光軸を規定値に合わせ、夜間走行に支障がないかを確認。
納車
修理内容と交換部品を説明し、安全運転を促す。
安全第一:ブレーキやタイヤなど安全部品は必ず規定値を満たすまで修理。
品質管理:部品組付け時のトルク、塗装後の色ムラ、電装系の動作確認などを徹底。
お客様への説明:修理前・修理後の状態を写真や部品現物で見せると信頼度が高まる。